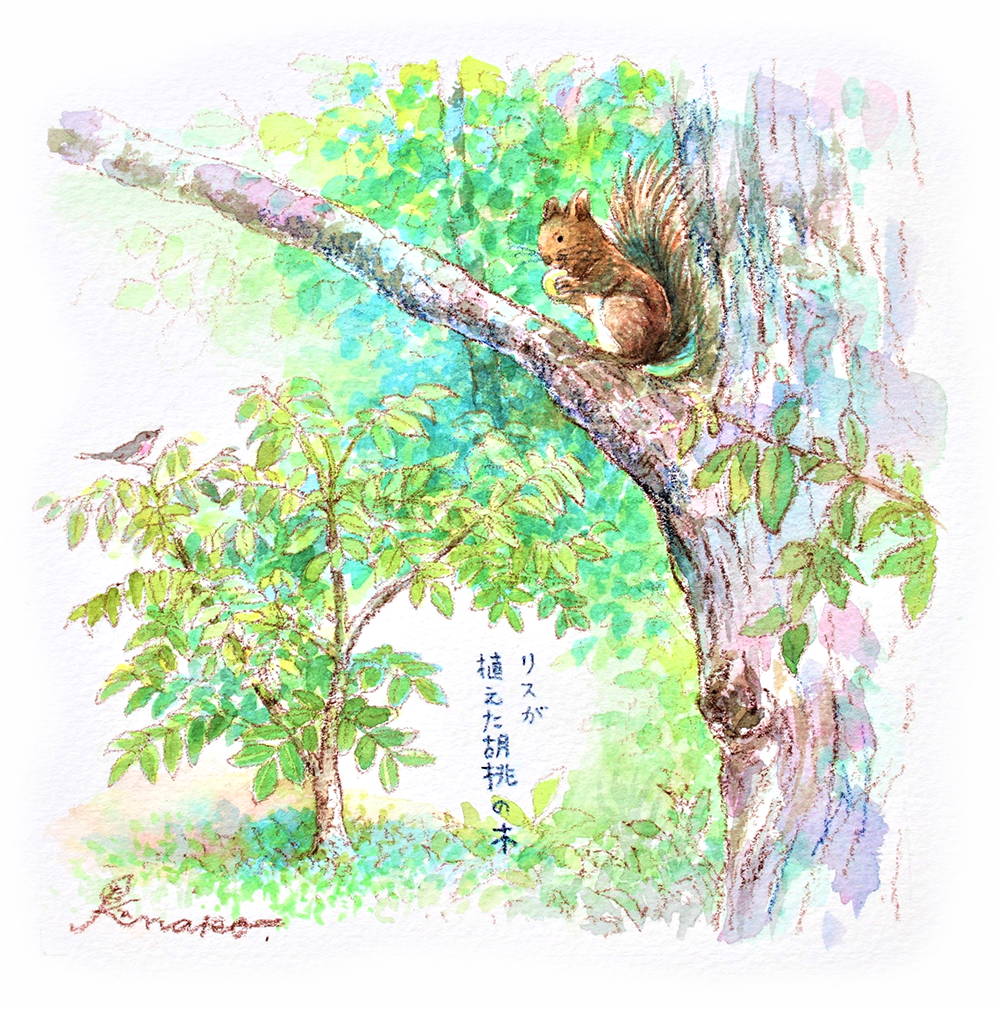理学療法士 杉山 貴規

from 杉山貴規 都内カフェ
もう9月になりましたが、暑さが残る日々が続いていますね。
夏の疲れがどっと出るこの時期、体には気をつけましょう!
っていうか、
なんと!この自分が先日体調を久々に崩したんですよ。
体を崩したっていうのは、最近の某コ◯ナウィルスではなかったですが、
朝、鏡を見ると上唇の上に赤い発疹が、、、
ヘルペス???
ま〜ほっておけば治るかなぁ〜と思っていたんですが日に日に痛くなるし、発疹が大きくなる一方。
このままいったら、たらこ唇がさらに大きくなる。
そう思って、皮膚科に受診したんです。
私「先生、ここにヘルペスができていて、痛いんですよ。」
先生「うわぁ〜、本当だね。おおきいね。・・・ってここにも発疹あるけどこれ痛くない」
自分も知らないうちに左頬から耳にかけて小さい発疹の行列ができていたんです。
全然気がつかなかった。
すると先生が
先生「それ帯状発疹だね。これ。痛いでしょ?他にも痛いところない?頭とか。口とか」
自分「痛いです。」
言われてみれば、ヘルペスができる随分前から、耳から頭部にかけて激痛が走っていたんです。
自分では、マスクのつけすぎで偏頭痛になったんだろうと思っていたんですが、その原因が帯状発疹だとは思いもよらなかったんです。
(え〜〜〜帯状発疹か〜)
先生「きっとね〜、疲れとストレスが原因だよ。これ1週間飲めば治るから飲んでおいて」
帯状発疹というと、病院でよく見たものです。
入院患者さんが、よくなっていて、看護師さんがアズノール(塗り薬)を塗りたくっていたのをよく見ました。
なので、ご高齢の方がよくなる病気みたいな感じで思っていたんで、自分の中ではものすごくがっかり。
そんなもんで、規則正しい生活と先生からもらった抗生剤とアズノールを使って今ではもう完治。
ストレスと睡眠不足が招いた結果
体が悲鳴をあげていたなんて思いもよりませんでした。
このように、自分の知らないところで体が悲鳴をあげて、最終的に痛みを生じてしまうっていうことは怪我でもよくあることです。
例えば、今回話すテーマなんですが、
セーバー病(踵の痛み)なんかもその一つです。
一種の成長痛ってやつなんですが、転んでしまった、相手にぶつかった、何かにぶつけたという外傷的なものではなく。
オーバーワークと疲労が合わさって痛みを生じるやつなんですよね。
じゃ〜このセーバー病(踵の痛み)をどのように治し・予防していくのかを今回話していきたいと思います。
まず初めに、セーバー病とはどういう怪我なのか?
それをまず理解していきましょう。
怪我の中身を理解することで、このあと話す内容がグッと入ってきます。
この記事を書いた人